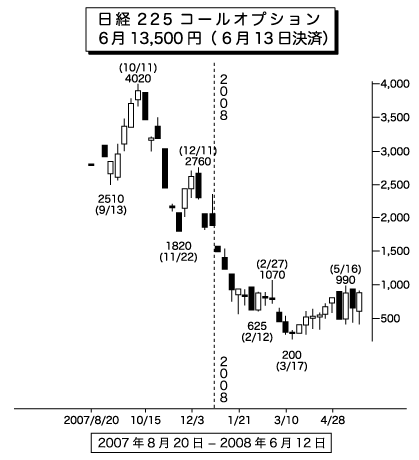| (一)エネサーブを大和ハウスが買収。 |
(1)エネサーブの50%を保有する大和ハウスは30日引け後にエネサーブを完全買収すると発表した。
(2)買収価格609円は当日の大引け値417円を192円、46%上回り、株主としては十分満足できる条件であった。
(3)クラブ9の推奨銘柄から短期間に加ト吉(JT)、富山化学(富士フイルム)に次ぐ第3の買収銘柄が出た。
(4)買収はその企業の価値を高く評価する企業があればこそ実現する。クラブ9の推奨銘柄は年間10〜20社に過ぎないから、買収に遭遇した確率はきわめて高い。私は事業資質や資産価値など、経営者の視点で企業の投資価値を割り出しているが、その視点が間違いでなかったことが証明されたと思う。
(5)しかし買収価格の設定には大差がある。JTは割安な加ト吉の株価に配慮して先に買収を表明し、株価の上昇を待って買収価格を決定した。これに対して富士フイルムは富山化学の買収価格を最低に抑えるための条件を恣意的に設定し、おまけに上場廃止を告知して株主に即時売却を迫った。完全買収、上場廃止を狙うのであれば、大和ハウスのように買収価格に十分なプレミアムを付与するべきであった。武田やエーザイが米国で開発型の製薬会社を買収した際の条件設定に比べても富山化学は異常に低い。私には株主が反乱を起こさないことが不思議であった。
(6)アデランスの株主総会で先週、株主軽視の経営者に対して株主が反乱を起こし、経営権が外国資本の手に渡った。日本の経営者は他山の石とするべきだろう。
(7)かねてから私は住友金属鉱山が外国資本によって買収される可能性が高いと指摘している。中国に次いで、ロシアが大型の国営ファンドを立ち上げると予想されるが、両国の国営ファンドは国家戦略の一翼を担う可能性がある。そんな時代に日本を代表する資源株・住友金属鉱山の経営者は情報開示に消極的なために保有資産に対する時価総額が過小で、外国資本の買収の標的となりやすい。
(8)このところ電池関連株が太陽光発電や電気自動車と共に注目を集めていた。エネサーブの買収は、他の電池関連株の株価を刺激するかも知れない。
|
|
| (二)オプションの暴落、暴騰。 |
|
(1)チャートは6月13日決済、日経225コールオプション 13,500円の週足である。昨年8月20日に上場された後、10月11日には4,020円の高値を記録したが、今年の3月17日には200円へ大暴落した。1枚400万円が20万円へ、20分の1に大暴落したのだから、買い下がった買い方は次々に破産した。
(2)しかし3月17日を境に相場は反騰に転じ、5月30日には1枚20万円から100万円へ、5倍に急騰した。暴落過程で大もうけした投資家は2匹目のドジョウを狙って売り上がり、天国から地獄に転落したのである。
(3)オプション取引は株式市場における丁半博打である。私は、平素はオプション取引に無関心であるが、相場が底入れしたと見た時に、コールオプションを1〜2枚限定で買ってみるが、今回ほど極端な暴騰暴落に出会ったことがない。
(4)暴落で大勝利した売り方がわずか2ヶ月後に窮地に追い込まれて行く状況を見て、私は本格的な相場の底入れを予感した。
(5)エコノミストも日経も証券界も弱気論の看板を下ろさないが、現実の株価は彼らが掲げていた戻りの壁を苦もなく、次々に突破した。オプションを見れば一目瞭然、弱気派の多くは心理面でも担保面でも窮地に追い込まれている。
|
|
| (三)30兆円の評価損の行方。 |
|
(1)4月にIMF(国際通貨基金)が、3月末現在で30兆円に達したサブプライム関連証券の評価損が2年後に95兆円に激増するという予測を発表し、グリーンスパン前FRB議長を初め大半のエコノミストがその悲観論に追随した。
(2)しかし私は第2四半期(4〜6月)に、評価損が評価益に転じる可能性があると主張している。サブプライム関連証券はすでに80%以上暴落しており、ゼロになっても下げ幅は20%、6兆円に過ぎない。
(3)一方、FRBは3月のベアースターンズ救済直後に投資銀行に対して30兆円の資金枠を設定し、保有証券を米国国債と交換すると発表した。30兆円という資金枠はこれまでに世界中の金融機関が計上した評価損に匹敵する。私はFRBの断固たる決意を見て、サブプライム問題は終わったと感じた。
(4)サブプライム関連証券がこれ以上下がらないと見れば、80%も大暴落したサブプライム関連証券は絶好の買い場である。
(5)私は6月には金融機関の評価損が評価益に逆転したことを示す情報が表面化し、ニューヨークダウが保合を上放れると思う。
(6)その場合は評価損が大きな金融機関の反発力が大きい。3兆円の評価損を計上したシティバンクの指標性に注目したい。
|
|
| (四)一人勝ちしたオイルマネーの行方。 |
|
(1)前回に私は金融市場を麻雀に例えて、4人のうち3人がハコ点となれば残る一人が必ず利益を独り占めしている、と述べた。一人勝ちしたのは産油国である。
(2)エコノミストは負けた3人の惨状を分析して弱気論を構成しているが、一人勝ちした産油国のオイルマネーの行方を無視している。
(3)エコノミストはデータによって景気や業績や株価を予想するが、公表されたデータは過去の事実である。これに対して巨額の利益を独り占めした産油国はその資金を必ず株式、債券、不動産等に投資するが、彼らは決していつ、何を買うかを明かさない。資金量が大きければ大きいほど、深く、静かに潜行して買い付けるから、データ至上主義のエコノミストには見えない。
(4)そこで私は、東京市場の堅調は政府系ファンドを含む新規のオイルマネーが流入したからではないかという仮説を立てた。そう推定しないと東京市場の需給関係の逆転現象を説明することができない。
(5)オイルマネーが東京市場に流入したとすれば、ニューヨーク市場に流入するのは時間の問題となる。私の推定が間違いでなければ、需給関係から見てもニューヨークダウの保合放れが近い。
|
|
閑話休題。
谷川健一「孤立こそ栄光の証し」。 |
|
(1)日経「私の履歴書」5月31日付けの最終回で、谷川健一氏は「孤立こそ栄光の証し」という見出しを掲げて次のように述べておられる。
(2)「独学者は昨日まで橋のたもとでコモをかぶって寝ていて、やおら立ち上がり、徒手空拳で闘いをいどみ、自分の力で国を奪い取る戦国時代の野武士に似ている。奪い取った知識は自分の血となり肉となって躍動する。孤立しているが、世の独創的な発想や研究は自分で学び、自分で考えることからしか生まれない。」
(3)「南方熊楠は自分の学問を『自学』と称してはばからなかった。折口信夫は『一己の学』つまり自分一個の学問であると言い放った。彼らは孤立の道を歩むことを余儀なくされたが、孤立こそ独学者のかけがえのない栄光の印である」。
(4)ちなみに谷川健一氏は中年になって民俗学の研究に乗り出し、90歳代で「文化功労者」を受賞された。前掲の文章は受賞祝賀会における挨拶の一部である。
(5)おこがましいが、私も中年を過ぎて自立し、孤立を恐れず、自説を掲げてきた。その間多くの間違いを犯し、読者に迷惑をかけたが、しばしば相場の天底を的中させることも出来た。私は自由に自説を述べるために、早くからすべての対外活動を停止して無料のホームページ「クラブ9」をわが砦としている。
(6)7年前に私は『不動産が値上がりする!』(主婦と生活社)を出版して不動産相場の底入れを予測した。しかし私が誇りとしたいのは、底入れ後の不動産相場の回復過程の予測である。すなわち不動産は大企業や金持ちの手から無数の個人投資家の手に渡り、不動産相場は利回りによって形成される。値上がりは東京都心の一角に発して、点から点へ、点から線へ飛び火するが、点が面に広がるには時間が必要だ、と述べた。不動産投信が上場される前で、弱気一色の不動産市場でその革命的なインパクトを予想した論評は皆無であった。
(7)今回の株式相場についても、私は単に底入れを予想しているわけではない。底入れの徴候を指摘し、回復への筋道を具体的に示すことに力を注いでいる。予測が的中したかどうかの評価は時間の経過に委ねるほかない。
(8)孤立に耐えるためには忍耐と度胸と見識が必要である。私にとって、谷川健一氏は目標であり、励ましである。 |
![]()
![]()