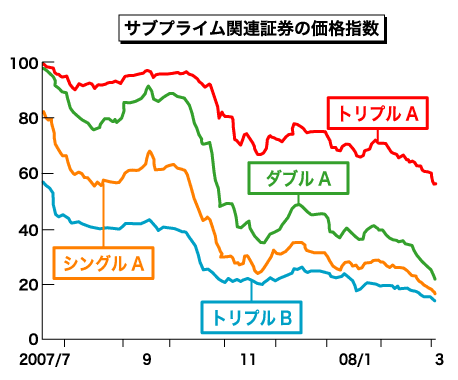(1)株式市場には「人の行く、裏に道あり、花の山」という格言がある。「知ったらしまい」という格言もある。
(2)どんなに大きな悪材料、好材料も、みんなが知ってしまえば株価は織り込み済みとなる。株価は未知の材料に対して反応する。株価がどこまで悪材料を織り込んだか。それが問題である。
(3)例えば、外資系証券が3月決算でサブプライム関連の評価損が拡大すると見て銀行株を格下げした。本決算で減益となっても予想の範囲であれば、株価は悪材料出つくしで上がる可能性がある。
(4)例えば、相場の地合もエコノミストやマスコミの論調が弱気一色となれば、株価が悪材料を織り込んで、反騰の条件を形成する。
(5)例えば、東京市場の出来高や市場性はニューヨークに次いで高い。中国は時価総額で日本を上回るが、政府の保有株が90%を占めているから、市場性は新興市場並みに低い。それゆえ下落局面では東京市場がアジア市場のヘッジ売りの場となったのである。その結果、東京の先物市場と借り株市場で外国人投資家の大量のカラ売りが堆積したから、一旦反騰局面に転じると、買い戻しとヘッジ買いで東京市場が割高となる。エコノミストとマスコミは日本株の割安を日本経済の弱さに求めているが、筋違いの分析が多い。
(6)例えば、欧米の株式市場はサブプライム関連の損失、景況と業績の悪化、住宅の値下がりと在庫増、失業率の上昇、インフレの進行等々、山のような悪材料を次々に問題視したが、株価もまた暴落課程で悪材料を織り込んでいる。
(7)現在は悪材料を過剰に織り込み過ぎた局面だと私は思う。マスコミは悪材料探しに熱心のあまり、着実に成熟しつつある好材料を見落としている。
![]()
![]()