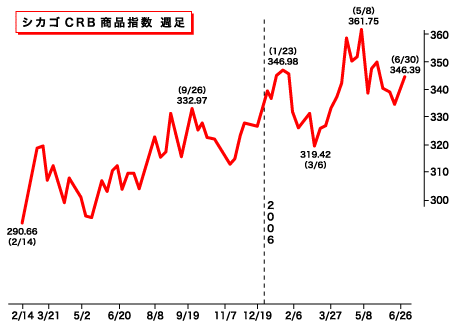| (一)騰勢が加速する国際商品相場。 |
(1)シカゴCRB商品指数は石油を初め、非鉄、貴金属、穀物、繊維など、広範囲の国際商品相場を織り込んだ代表的な商品指数である。
(2)CRBはすでに史上最高値を突破している。現在は短期的な調整を終えて、再度最高値更新へスタートを切ったところだと私は思う。
(3)21世紀に入って、商品相場の騰勢は衰えるどころか、尻上がりに加速している。
(4)私が商品相場を重視し、超強気を堅持する理由は簡単明瞭である。全世界の人口は60億人であるが、その半分の30億人がBRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)4ヶ国に集中している。その人口超大国がそろって年率10%の超高度成長を続けているのだから、ありとあらゆるモノの需 給関係が逼迫するのは当然で、騰勢を覆すほどの兆候は見えない。
(5)アメリカのインフレもまたBRICs4ヶ国の高度成長に起因しているのだから、バーナンキFRB議長がいくらアメリカの政策金利を引き上げてもアメリカの消費者物価指数の上昇を阻止することはできない。金融政策には限界がある。転機は近いだろう。
(6)私は国際商品相場の指標性を明快に認識しているかどうかで、楽観論と悲観論が別れると思う。以下に日頃のわが超楽観のシナリオをまとめて再説しておきたい。
|
|
| (二)世界経済の歴史的な構造変化。 |
|
(1)20世紀には欧米先進国が世界中で植民地を築き、植民地から収奪した安い原材料を用いて産業革命を起こし、世界貿易の利益を独占した。
(2)日本は過去30年間に欧米に追随することができたが、経済的な先進国と後進国の格差は歴然としていた。
(3)その格差を最初に破壊したのは第1次オイルショックであった。石油は自動車社会に不可欠なガソリンの原料となったが、合成繊維やプラスチックなど、工業製品にも不可欠の原料となった。
(4)一方、30年前に、イランは国王を追放して共和国となり、中東の遊牧民は植民地支配を脱出して独立国家を樹立した。彼らは次々に油井を国有化し、OPEC(石油輸出国機構)を結成して石油の価格支配権を確立した。折から需要が激増した石油相場が暴騰して第1次オイルショックが発生したのである。
(5)20世紀の終わりには中国が驚異的な2ケタ経済成長を開始し、インド、ロシア、ブラジルが追随した。
(6)その4ヶ国の頭文字をまとめてBRICsと呼ぶが、4ヶ国はみな人口超大国であった。地球上の全人口は60億人であるが、4ヶ国だけで半分の30億人を占めている。
(7)その30億人が超高度成長時代を迎えたから、石油、鉄、非鉄、貴金属、農産物、食肉、繊維など、ありとあらゆる国際商品の需給関係が逼迫した。
(8)このような世界経済の歴史的な構造変化を受けて、21世紀の初めにシカゴ商品指数は革命的な暴騰を演じたのである。
|
|
| (三)石油相場の大暴騰は商品相場高騰の先行指標。 |
|
(1)30年前の第1次オイルショックで10ドル台に暴騰した石油は今や70ドル台に大暴騰した。
(2)中国は高度成長を維持するために、世界市場で石油はもちろん、すべての工業用原材料と食料品の囲い込みに走っている。中国が世界最大の生産量を誇るトウモロコシでさえも輸出を禁止したほどである。
(3)インドのミタル財閥はあっという間に世界中の鉄鋼大手を買収し、一気に国際的寡占(かせん)時代の主役に躍り出た。
(4)アメリカのヘルプスドッジはカナダのインコとファルコンブリッジを買収し、銅、ニッケル、アルミなど、非鉄金属市場で寡占体制を確立する意志を鮮明にした。
(5)一方、BRICsに次いで中南米、アフリカ、アジアの経済的後進国が次々に石油、天然ガス、非鉄、鉄鉱石、金などの埋蔵資源の国有化をはかり、価格支配権を奪取しようとする動きが表面化しつつある。
(6)それらの状況は30年前の第1次オイルショック前夜をほうふつとさせる。石油相場の大暴騰は、その他の商品相場の一斉蜂起の先行指標である。
(7)私たちはいま、地球規模の産業構造の大変革期に遭遇しているのである。
|
|
| (四)商品相場と株式相場の長期上昇傾向は不変。 |
|
(1)かくして欧米と日本が世界経済の発展を牽引した時代は終わりつつある。
(2)しかしそれは一つの経済体制の終わりではなく、地球規模の拡大発展時代の始まりを意味している。短期的な混乱や波乱があっても、後戻りはないだろう。
(3)日本がいまバブル時代以来の成長力を回復したといっても年率2%程度に過ぎないが、中国やインドは10%成長を持続している。ヨーロッパでもロシアを含む旧東ヨーロッパ諸国がヨーロッパ全体の経済成長を牽引している。
(4)世界経済の主役が歴史的な交代期を迎えたことは歴然としている。
(5)石油相場は70ドル台に大暴騰したが、反落、暴落するよりも100ドル大台を目指す可能性の方が高い。そうなれば中東産油国にもっと巨大なドルが積み上がるから、日本株に対する外国人買いが増えることはあっても衰えることはない。
(6)20世紀には株式市場が大成長を遂げる一方で商品市場が低迷したが、21世紀には商品市場の高騰が株式市場をリードするだろう。60億人の世界人口がみな経済的な繁栄を追求すれば、モノの需給関係が構造的に逼迫するのは当然だからである。
(7)わが超楽観のシナリオに比べれば、エコノミストが指摘する悲観論はみな歴史的な視点を欠いたゆえの枝葉末節に過ぎない。
|
![]()
![]()